 建長寺にある「雲龍図」は創建750年記念事業の一環で、法堂(はっとう)の天井に描かれたものです。平成12年(2000)の完成。
建長寺にある「雲龍図」は創建750年記念事業の一環で、法堂(はっとう)の天井に描かれたものです。平成12年(2000)の完成。
建長寺は見どころが多く、境内の写真とあわせて紹介します。御朱印は最後に紹介します。
続きを読む
 江ノ島電鉄にはトンネルが一つだけあります。長谷駅と極楽寺駅の間にある「極楽洞(極楽寺トンネル)」です。鎌倉市景観重要建築物、土木学会選奨土木遺産に指定されています。鎌倉七切通しのひとつである「極楽寺坂」をトンネルで通過します。
江ノ島電鉄にはトンネルが一つだけあります。長谷駅と極楽寺駅の間にある「極楽洞(極楽寺トンネル)」です。鎌倉市景観重要建築物、土木学会選奨土木遺産に指定されています。鎌倉七切通しのひとつである「極楽寺坂」をトンネルで通過します。
続きを読む
 伊勢地方の民謡「伊勢音頭」で「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ 尾張名古屋は城でもつ」と歌われるほど、名古屋城は名古屋の象徴的存在です。現在、昭和20年に空襲で焼失した「本丸御殿」の復元工事が行われています。
伊勢地方の民謡「伊勢音頭」で「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ 尾張名古屋は城でもつ」と歌われるほど、名古屋城は名古屋の象徴的存在です。現在、昭和20年に空襲で焼失した「本丸御殿」の復元工事が行われています。
続きを読む

奥州市江刺区岩谷堂にある館山史跡公園(岩谷堂城本丸跡)はアジサイの名所です。 アジサイの見ごろは7月下旬ごろでしょうか。この地は、藤原経清と清衡親子が居住した砦館の跡とも伝えられています。
続きを読む

「前九年の役」で最後の砦として激戦地となった厨川柵、安倍館跡とされる盛岡市内の遺構を巡ります。
続きを読む

ブラタモリ(2015年7月11日放送)『仙台~伊達政宗は「地形マニア」!?~』では、伊達政宗が築いた「四ツ谷用水」を取り上げていました。番組で取り上げた場所を中心に仙台市内を巡ってみました。
仙台散歩としましたが、長い距離は車で移動です。地図は最後に紹介します。
続きを読む
室根山(895m)の8合目付近に室根神社(一関市室根町)はあります。「本宮」と「新宮」の2社が祀られる歴史ある神社です。境内奥の泉には「室根山三十三観音」が祀られています。
_thumb.jpg)
続きを読む
梅原猛著「日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る」 (集英社文庫)、著者が東北を旅しながら、原日本人と原日本文化を探し求めます。
梅原猛氏が東日本大震災復興構想会議の特別顧問だと知り、再度読み直してみました。
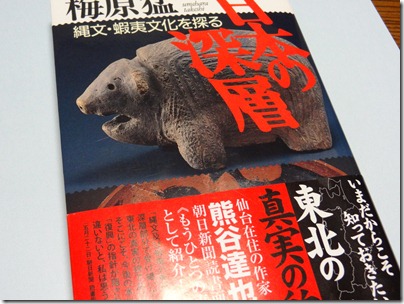
続きを読む
「胆沢城(いさわじょう)」(奥州市水沢区佐倉河渋田)は平安時代初期802年に坂上田村麻呂によって築かれた鎮守府(ちんじゅふ)です。古代城柵の跡地として、大正11(1922)年に国の指定史跡となっています。
_thumb.jpg)
続きを読む
「荒俣宏・高橋克彦の岩手ふしぎ旅」(実業之日本社)を読みました。同じ1947年生まれの荒俣宏氏と高橋克彦氏が独特の視点から謎が多い岩手の歴史を探訪します。岩手の隠れたパワースポット、隠された歴史をひも解きます。
昨年9月に遠野市で開催された「妖怪セミナーin遠野・第三回怪遺産認定式」で、お2人の対談を聞きましたが非常に面白い内容だったことを思い出します。
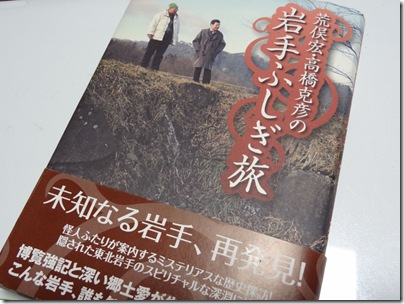
続きを読む
 建長寺にある「雲龍図」は創建750年記念事業の一環で、法堂(はっとう)の天井に描かれたものです。平成12年(2000)の完成。
建長寺にある「雲龍図」は創建750年記念事業の一環で、法堂(はっとう)の天井に描かれたものです。平成12年(2000)の完成。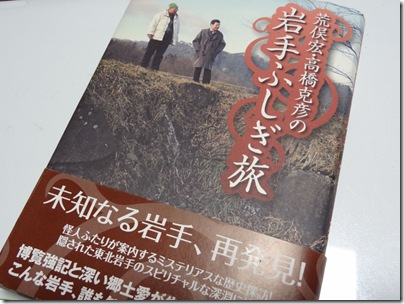






_thumb.jpg)
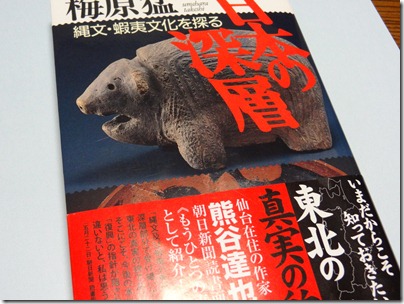
_thumb.jpg)
